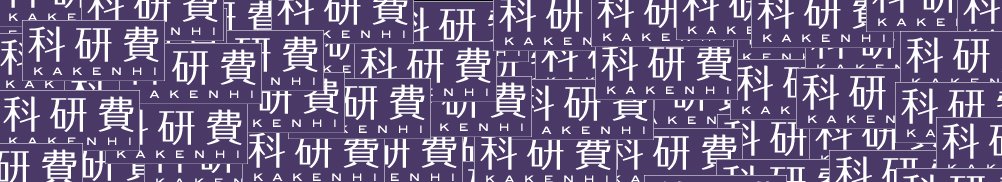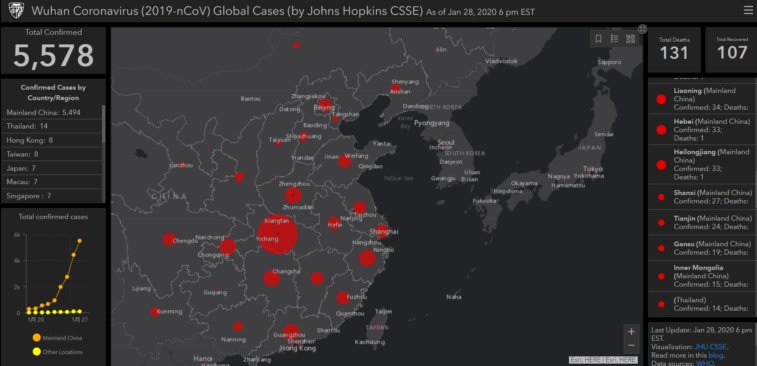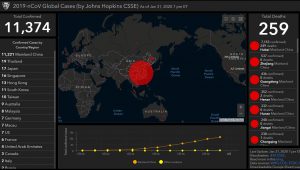末梢動脈疾患(PAD)とは
閉塞性動脈硬化症(ASO)
下の解説は、一般の人向けで病気の症状や治療方針などの解説が非常にわかりやすい。
初期の症状は足の冷え、しびれ、歩行困難(間欠性跛行)です。この段階で早期発見することが大切です。(末梢動脈疾患(PAD) 住友病院におけるチーム医療の実際 PDF)
- バージャー病に関する最近の知見とバイパス術の役割(茨城県バージャー秒患者と家族の会)
血管新生療法(Therapeutic Angiogenesis)とは
下の動画では、血管新生を利用した治療方法が紹介されています。末梢動脈疾患(peripheral arterial disease; PAD)に対する血管新生療法の応用に関しては、13:03から。
Frontiers of Regenerative Medicine: Therapeutic Angiogenesis to Reverse Heart Disease 2019/10/16 MoneyShow
血管新生療法(Therapeutic Angiogenesis)の効果
血管新生療法 この療法は新しい血管をつくりだし、足の血流不足を補うのが狙いで、薬物療法がきかない、血行再建術のできない患者さんに適応が考えられる方法です。わが国では現在、この治療法として患者さん自身の骨髄、または血液中の単核球の移植が、先進医療として認可され、有効であることが報告されています。(国立循環器病研究センター 循環器病あれこれ)
当社は、2019年3月、重症虚血肢を対象としたHGF遺伝子治療用製品の条件及び期限付製造販売承認を取得しました。これは、標準的な薬物治療の効果が不十分で血行再建術の施行が困難な慢性動脈閉塞症における潰瘍の改善を効能、効果又は性能とするもので、国内では初の遺伝子治療用製品となります。(アンジェス株式会社)
重症虚血肢に対する自家骨髄または自家末梢血単核球細胞移植は,閉塞性血栓血管炎に対して有効であるが,閉塞性動脈硬化症には良い報告がなく,現在,新たな細胞治療の供給源を模索している状況にある。(慢性動脈閉塞症の診断意義と血管新生治療について 北里医学 2018; 48: 11-17)
For approximately 2 decades, “therapeutic angiogenesis” has been studied as an investigational approach to treat patients with symptomatic PAD. Despite literally hundreds of positive preclinical studies, results from human clinical studies thus far have been disappointing. (Therapeutic Angiogenesis for Peripheral Artery Disease Lessons Learned in Translational Science JACC Basic Transl Sci. 2017 Oct; 2(5): 503–512.)
The results of this review do not support the use of therapy with the growth factors FGF, HGF or VEGF in people with PAD of the lower extremities to prevent death or major limb amputation or to improve walking ability. However, … (Growth factors for angiogenesis in peripheral arterial disease 08 June 2017 cochranelibrary.com)
下は2016年のレビュー論文。細胞移植の実際、効果、この治療法の展望など。
細胞による血管再生医療は,成人の末梢血の中に骨髄から動員された血管内皮前駆細胞が存在することが確認され,生後の血管新生に寄与することが明らかにされたことに始まる1).(末梢動脈閉塞症に対する血管再生医療 京府医大誌 125(11),759~767,2016 PDF)
- Isolation of putative progenitor endothelial cells for angiogenesis. Science 1997;275:964-967.
血管新生療法(保険適用外)
わが国では先進医療として,末梢血幹細胞移植がいくつ
かの登録施設で行われている.末梢血単核球移植,自己骨髄単核球細胞移植,HGF や VEGF,FGF の遺伝子治療は未承認である.いずれも治療法として確立されていない.(36ページ)研究的治療(保険適用外)として末梢血幹細胞移植(先
進医療に指定),末梢血単核球移植 520),自己骨髄単核球細胞移植 521),VEGF 522)や HGF 523)などの遺伝子治療,などによる血管新生療法が報告されている.しかし,臨床症状の改善は認められるものの明確な血管新生の証明はなされておらず,今後の研究結果が待たれる.(65ページ)(末梢閉塞性動脈疾患の治療ガイドライン (2015 年改訂版) Guidelines for the management of peripheral arterial occlusive diseases (JCS 2015) PDF)
このように血管再生治療は治療抵抗性 PAD に対して,各種の臨床研究を通じ て徐々に安全性と有効性が一般に認識され,PTA やバイパス術が不可能な難治 性症例の最後に考慮され得るべき最新治療となりつつある.(難治性末梢動脈疾患に対する血管再生治療の最前線 日耳鼻 118: 1281―1288,2015 PDF)
個々の治療法の効果に関しては、下の日本語のレビューが非常に詳細。一部を抜き出して紹介。各論はリンク先PDFを参照。
CLI に対する治療は薬物療法や運動療法は無効であり、まず血行再建による下肢血流の改善を考えなければならない。CLI 症例では inflow である腸骨動脈や浅大腿動脈領域よりも、膝下動脈に病変を有する事が多い。安静時疼痛のみで、組織欠損のない症例では inflow の血行再建のみで症状は改善するが、組織欠損がある症例では下腿動脈も含めた完全血行再建が必要となる。血行
再建の適応がなければ、血管新生療法、保存的加療、下肢切断を考えることになる。(31ページ)1990 年代までに血管内皮成長因子 vascular endothelial growth factor (VEGF)、酸性線維芽
細胞成長因子 acidic fibroblast growth factor (aFGF)、塩基性線維芽細胞成長因子 basic
fibroblast growth factor (bFGF)、肝細胞成長因子 hepatocyte growth factor(HGF)、胎盤成長因子 placental growth factor (PlGF)など、血管新生現象を in vitro および in vivo で促進する成長因子が相次いで同定された。これらの血管新生因子の遺伝子やタンパクの投与により、組織虚血を軽減しようとする治療的血管新生が臨床的に試みられてきた。1997 年にAsaharaら1)は、成人末梢血中のCD34 陽性細胞が血管内皮前駆細胞(endothelial progenitor cell: EPC)であることを発見した。以後、骨髄または末梢血由来のEPCおよび単核球(EPCを含む雑多な細胞集団)や間葉系幹細胞(mesenchymal stem cell: MSC)などを移植して、虚血下肢筋肉内における新規血管形成治療が試みられるようになった。血管新生因子を投与すると、既存の血管内皮細胞の増殖・遊走による血管新生に加えて、骨髄からの EPC の動員を介した血管発生も促進される。逆に幹細胞/前駆細胞移植では移植細胞による血管発生のみならず、移植細胞から分泌される血管新生因子による血管新生も惹起される。したがって、両治療法の作用機序に厳密な違いはないため、最近では血管再生治療と総称されることが多い。(37ページ)(平成24年度次世代医療機器評価指標作成事業 重症下肢虚血分野 審査WG報告書 平成25年3月 72ページPDF)
In this Review, data from phase II and III clinical trials of therapeutic angiogenesis in patients with PAD will be presented and discussed. Potential explanations for the limited success of therapeutic angiogenesis in humans will be viewed in the context of advances in our understanding of the complex mechanisms underlying angiogenesis and vascular remodelling. (Nat Rev Cardiol , 10 (7), 387-96 Jul 2013 Therapeutic Angiogenesis for Critical Limb Ischaemia PubMed)
- 遺伝子治療臨床研究実施計画の重大事態等報告について(平成 21 年 6 月 30 日 第 50 回科学技術部会) 【九州大学病院】課題名:血管新生因子(線維芽細胞増殖因子:FGF-2)遺伝子搭載非伝播型組換えセンダイウイルスベクターによる慢性重症虚血肢(閉塞性動脈硬化症、バージャー病)に対する血管新生遺伝子治療臨床研究(UMIN-CTR)
難治性末梢動脈閉塞性疾患(PAD)に対する新しい治療法として血管新生療法が注目され、国内外で臨床的評価が行われている。しかしながら、初期において有望な成績が示唆されていたにもかかわらず、多施設二重盲検による第II相試験では、多くののプロトコールが失敗に終わっている。
治療的血管新生療法への初期の試みは血管新生因子蛋白を用いたものであり、数年後より血管新生因子を用いた遺伝子治療が開始、そして最近では骨髄単核球細胞や血管前駆細胞を比較的多く含むと考えられているCD34陽性細胞などによる細胞療法も試みられている。(サイトカインによる末梢動脈閉塞性疾患に対する血管新生療法:その現状と将来 脈管学 Vol.47, 2007)
- Non-option 虚血症例に対する運動療法の考え方(冠疾患誌 2006; 12: 58-60 )
下は少し古いですが2004年のレビュー論文。
Therapeutic angiogenesis is an application of biotechnology to stimulate new vessel formation via local administration of pro-angiogenic growth factors in the form of recombinant protein or gene therapy, or by implantation of endothelial progenitor cells that will synthesize multiple angiogenic cytokines. Numerous experimental and clinical studies have sought to establish ‘proof of concept’ for therapeutic angiogenesis in PAD and myocardial ischaemia using different treatment modalities, but the results have been inconsistent. (Therapeutic Angiogenesis in Peripheral Arterial Disease: Can Biotechnology Produce an Effective Collateral Circulation? July 2004 Volume 28, Issue 1, Pages 9–23. Europiean Journal of Vascular & Endovascular Surgery ejves.com)
1997年
1997 年にタフツ大学の浅原らは,成人の末梢血中に内皮前駆細胞(endothelial progenitor cell : EPC)が存在することを初めて報告した.EPC は,フィブロネクチンに付着する 紡錘状の細胞として分化し,ネットワークを形成する.このEPC の発見により,成人にお ける血管新生の概念が大きく変化した.すな わち,既存の内皮細胞が分裂・増殖してネットワークを形成する angiogenesis(血管新生)型と考えられていたものが,流血中の内皮前駆細胞がネットワークに加わって血管をつくることで,これまで胎生期にしか起こらないと考えられていた vasculogenesis(血管発生)型の血管再生が成人においても起こっている可能性が示唆された.(細胞移植による血管新生療法)
参考
- 末梢血管疾患 患者さんへ(京都大学心臓血管外科)
- 閉塞性動脈硬化症とバージャー病に対する血管新生遺伝子治療の臨床応用(PDF)
- 末梢・腸骨動脈ステント(第38回日本IVR学会総会「技術教育セミナー」)
- HGF 遺伝子による血管新生遺伝子治療 外科的治療の適用が困難であり、内科的治療に抵抗性の安静時疼痛又は潰瘍症状を有する慢性動脈閉 塞症(閉塞性動脈硬化症及びビュルガー病)の症状を改善する標準的な治療法は存在せず、リスクフ ァクター除去や保存療法により経過観察せざるを得ず、趾肢切断となる患者が後を絶たない状況であ る。 HGF 遺伝子(AMG0001)を用いた血管新生療法は、標的(筋肉)細胞内に導入された HGF 遺伝子に より発現する HGF が血管新生と血流増加をもたらし、虚血症状を改善する治療法であり、慢性動脈閉 塞症(閉塞性動脈硬化症及びビュルガー病)の治療薬としての効果が期待される。病変部位局所での 継続的な HGF 産生を実現する AMG0001 による遺伝子治療は、局所での虚血状態が慢性的な症状を呈 するに適した画期的な先進的な治療であると考える。代替治療が困難な慢性動脈閉塞症(閉塞性動脈硬化症又はビュルガー病)患者に対する AMG0001 の筋 肉内投与の有効性及び安全性を検討するために、同患者を対象に以下の方法で治療を行い、主要評価 項目を(1) Fontaine 分類 III 度の患者:安静時疼痛(VAS)の改善(投与前値から 20 mm 以上減少した場 合を「改善」と定義)、(2) Fontaine 分類 IV 度(潰瘍)の患者:潰瘍の改善(:投与前値から 75%以下に 潰瘍が縮小した場合を「改善」と定義する)とする多施設共同前向き非盲検単群試験。予定登録症例 数は 6 例。
- 閉塞性血栓性血管炎(ウィキペディア)(Thromboangiitis Obliterans: TAO)末梢動脈に閉塞性の内膜炎を起こし、末梢部に潰瘍や壊疽を引き起こす病気。… 発見者であるレオ・ビュルガーにちなんだ名前である Buerger’s disease として、ビュルガー病(ドイツ語読み)或いはバージャー病(英語読み)とも呼ばれる。
循環器疾患
循環器疾患最新の治療2020-2021(南江堂)の目次を参考に循環器疾患を纏めておきます。
心不全
1 急性心不全
2 HFrEF
3 HFmrEF
4 HFpEF(拡張不全)
5 新世代植込み型補助人工心臓
6 心不全に対する心臓リハビリテーション
7 心不全の緩和ケア
8 心臓移植
不整脈
1 心臓突然死
2 徐脈性不整脈
3 期外収縮(心房,心室)
4 心房細動:心原性脳梗塞予防
5 心房細動:リズムコントロール
6 心房細動:レートコントロール
7 心房粗動
8 上室頻拍,WPW症候群
9 特発性心室頻拍
10 基礎心疾患に伴う心室頻拍・心室細動
11 不整脈治療薬の催不整脈作用
12 J波症候群(Brugada症候群,早期再分極症候群)
13 QT延長症候群
14 心臓ペースメーカの選択と植込み患者の管理
15 植込み型除細動器(ICD)
冠動脈疾患
1 急性冠症候群
2 急性心筋梗塞に伴う機械的合併症
3 冠攣縮性狭心症
4 PCI
5 PCIと抗血栓療法
6 冠動脈疾患・心筋梗塞後のリハビリテーション
7 冠動脈疾患の薬物療法
8 冠動脈バイパス術
9 川崎病
弁膜疾患
1 僧帽弁狭窄症
2 僧帽弁閉鎖不全症:一次性
3 僧帽弁閉鎖不全症:二次性
4 大動脈弁狭窄症
5 大動脈弁閉鎖不全症
6 感染性心内膜炎
7 生体弁・機械弁の選択と管理
心筋疾患
1 急性心筋炎
2 拡張型心筋症
3 肥大型心筋症
4 拘束型心筋症
5 不整脈原性右室心筋症
6 心臓サルコイドーシス
7 周産期(産褥)心筋症
8 その他の二次性心筋症(Fabry病)
心膜疾患,腫瘍
1 急性心膜炎
2 収縮性心膜炎
3 心膜液貯留,心タンポナーデ
4 心臓腫瘍
先天性心疾患
1 心房中隔欠損
2 房室中隔欠損(心内膜床欠損)
3 心室中隔欠損
4 動脈管開存症
5 Ebstein病
6 Valsalva洞動脈瘤破裂
7 先天性心疾患:Fallot四徴症術後の管理と問題点
8 先天性心疾患:修正大血管転位の管理と問題点
9 Fontan手術後の遠隔期管理と問題点
10 先天性心疾患と妊娠・出産
肺循環
1 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
2 肺動脈性肺高血圧症
3 膠原病に伴う肺高血圧症
大動脈疾患
1 Marfan症候群,大動脈弁輪拡張症
2 高安動脈炎(大動脈炎症候群)
3 急性大動脈解離
4 胸部大動脈瘤
5 腹部大動脈瘤
末梢血管疾患
1 閉塞性動脈硬化症(Arterio-sclerosis Obliterans ASO)
2 腎動脈狭窄症
3 静脈血栓塞栓症(じょうみゃくけっせんそくせんしょう, Venous thrombosis; VTE)
高血圧症
1 本態性高血圧:ガイドラインに沿った治療戦略
2 白衣高血圧と仮面高血圧(早朝高血圧)
3 高齢者の高血圧
4 高血圧管理のための生活指導
5 二次性高血圧
脳血管障害
1 脳梗塞
2 頭蓋内出血
3 脳動脈瘤
4 頸動脈狭窄症