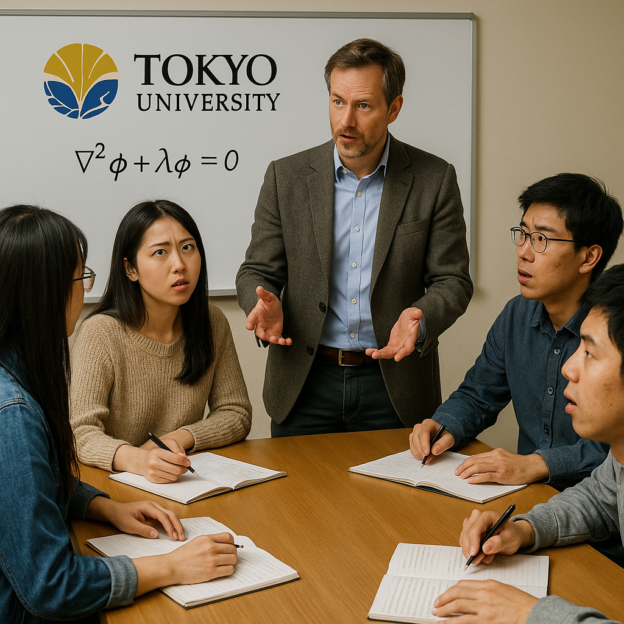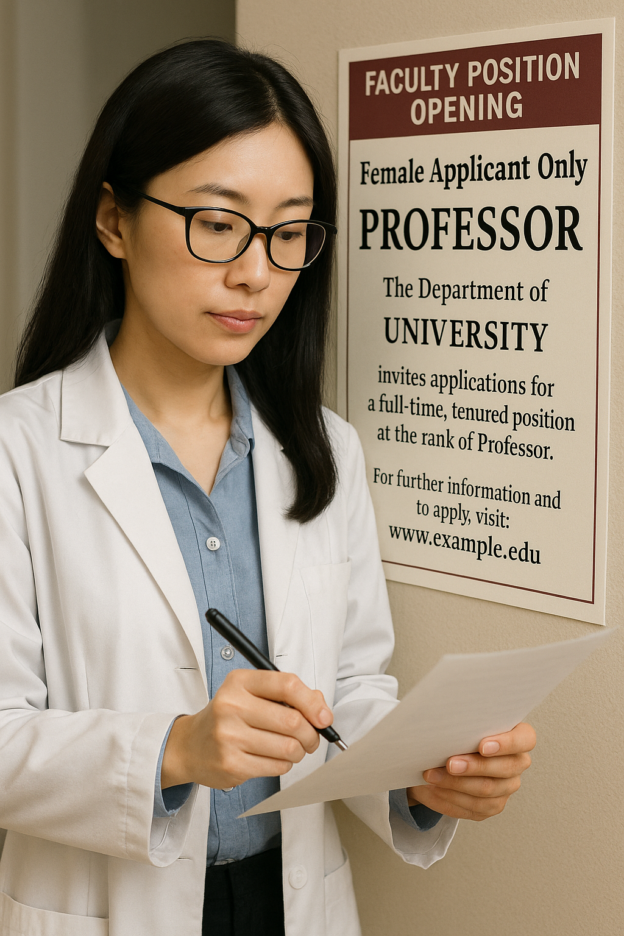ChatGPT 4oに申請書の書き方を具体的な例を交えて示してくれるように頼んでみました。テーマは全て架空(こちらが研究領域を大雑把に指定した際に、ChatGPTによって具体的に示されたもの)です。自分はDCに出したこともなければ、申請書の様式を見たことすらなく、以下の研究テーマに関しても完全にど素人なので、どれくらいのデキなのかに関しては全くわかりません。
以下、アウトライン程度ですが、それぞれの項目に厚みを持たせるように指示してChatGPTに文章の肉付けをさせることはできるのだろうと思います。
ここで示したものは、知識ゼロ、労力ゼロ、時間ゼロ(3秒)で吐き出されたものなので、採択されるための最低レベル以下だろうと思います。そういうつもりで参考にしてください。専門領域にいるDC応募者(人間)なら、これらよりもはるかに優れた申請書を作れるはずです。
生成AIの活用による科学的知の生成プロセスの変容とその規範的影響の実証的研究
**「生成AIを用いた科学研究の方法論の変化」**に関するDC1申請書の架空記入例をご用意します。以下のテーマはやや理論と実証を組み合わせた社会情報学・科学技術社会論(STS)寄りの内容ですが、コンピュータサイエンス・科学哲学・研究倫理などの観点とも接続可能です。
✅ 研究課題名
生成AIの活用による科学的知の生成プロセスの変容とその規範的影響の実証的研究
✅ 研究目的および学術的背景
大規模言語モデル(LLMs)を中核とする生成AI技術は、近年急速に高度化し、科学研究のあらゆる局面――仮説設定、論文執筆、コード生成、データ分析、査読など――において実際に用いられつつある。このような技術の導入は、単なる「効率化」にとどまらず、科学的知の構築プロセスそのものの構造を変容させる可能性がある。
一方で、現段階では生成AIの研究支援的使用は制度的にも規範的にも整備が追いついておらず、その活用の実態やそれに伴う認識変容についての学術的理解は未成熟である。
本研究の目的は、生成AIを利用する科学者たちの認識・行動の変化を実証的に明らかにし、科学的知の「生産過程」の構造的変容とその意味を理論的に再定式化することにある。これにより、AI時代の科学方法論・研究倫理・知の信頼性に関する議論へ新たな枠組みを提供する。
✅ 研究計画・方法
- 科学者における生成AIの利用実態の調査(質的・量的アプローチ)
日本国内の若手研究者を対象に、生成AI(ChatGPT、Bard、Claudeなど)の利用経験に関するアンケート調査と半構造化インタビューを実施。使用目的(例:構想メモ、論文の下書き、レビュー応答など)とそれに伴う意識変容(例:主体性の感覚、知的創造性の再定義)を定量・定性的に把握する。
- AI利用の文脈における知的生産プロセスの分析(ケーススタディ)
論文執筆過程を追跡可能な複数の事例に対し、バージョン管理記録、プロンプトの内容、修正履歴などを分析し、「人とAIの共著的構造」がどのように形成されるかを可視化・モデル化する。
- 科学的知の社会的構築に関する理論枠組みとの照合
STS(Science and Technology Studies)や行為者ネットワーク理論(ANT)を援用し、「AIを媒介とした知の生成過程」が従来の科学的実践とどう異なるのかを分析。従来のMerton的規範(再現性・客観性)との緊張関係も検討。
✅ 先行研究との差異と独創性・着想の経緯
生成AIをめぐる議論は、倫理・誤情報・プライバシーといった問題に集中してきたが、科学知の形成プロセスそれ自体の変容を「現場の研究者の認識」に基づいて実証的に検討する試みは限られている。
本研究の独創性は、科学を生産する実践的主体としての研究者の視点から、生成AIの影響を「知の生産過程の変容」として捉える点にある。また、単なる意識調査にとどまらず、プロンプト・履歴・生成物の記録をもとに知の生成構造を可視化するという方法論的工夫を含んでいる。
この着想は、ChatGPTを日常的に使っている研究者との会話を通じて、「自分が書いているのか、AIが書いているのか分からなくなる」という発言に触れたことに端を発する。「知の所有」や「創造性」の意味が再定義されつつあるという直感が、本研究の出発点である。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究は、AI技術が知的活動に介在することによって、科学的知の生成・伝達・評価の枠組みがどう変容するかを明らかにするものである。これは、AI時代における研究倫理、オーサーシップ、査読制度の再設計、科学的方法論の再構築といった課題に対する基礎的知見を提供する。
さらに、教育現場や研究機関で生成AIをどう位置づけるかといった制度的課題にも寄与しうる。将来的には、科学技術政策や研究評価制度への応用的インパクトも期待される。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私はこれまでに、科学技術社会論(STS)および情報社会論を基盤に、研究者の実践や学術コミュニケーションに関する定性的・定量的研究を行ってきた。質的調査(インタビュー・参与観察)とテキストマイニングによる量的分析を組み合わせた経験があり、Pythonによるデータ分析にも一定の習熟がある。
2024年度には、日本社会情報学会にて関連する研究発表を行い、学会誌への投稿も準備中である。これらの経験を活かし、本研究課題を構想から実施・分析・発信に至るまで、一貫して自律的に遂行する体制を整えている。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、生成AIが科学の知的実践に与える影響について高い関心を持ち、学部時代より一貫して社会情報学的観点からの研究に取り組んでいる学生である。本人は文献調査・データ収集・分析・執筆のすべてを独力で遂行できる能力を有し、理論的思考と実証的感覚を兼ね備えている点が特に優れている。
今回の申請課題は、AI時代の科学方法論と研究倫理の再構築という重要かつ新規性の高いテーマに取り組むものであり、学術的・社会的意義ともに極めて高いと評価できる。本人の研究遂行能力と探究心を踏まえ、特別研究員(DC1)として強く推薦する。
生成AIの科学研究への導入が再現性に与える影響の分析と規範的評価:科学的信頼性の再構築に向けて
以下に、生成AIと科学の再現性危機(reproducibility crisis)との関係性をテーマとした、日本学術振興会特別研究員(DC1)申請書の架空記入例をご紹介します。科学哲学・科学技術社会論(STS)・情報科学の交差領域を意識した構成です。
✅ 研究課題名
生成AIの科学研究への導入が再現性に与える影響の分析と規範的評価:科学的信頼性の再構築に向けて
✅ 研究目的および学術的背景
近年、心理学・生物医学・経済学をはじめとする複数の科学分野において、「再現性危機(reproducibility crisis)」と呼ばれる現象が報告されている。すなわち、既報研究の追試が失敗する割合が予想以上に高く、科学的知の信頼性そのものが揺らいでいるという問題である。
このような状況下で、生成AI(例:ChatGPT、Code Interpreter、AutoGPT等)が研究活動に急速に取り入れられており、仮説立案、論文執筆、コード生成、統計解析など、あらゆる局面において人間とAIの協働が進んでいる。しかし、生成AIによって生み出された知的成果物の再現性・検証可能性については、体系的な評価がなされていない。
本研究では、生成AIの研究利用が科学的再現性に与える具体的影響を多面的に検討し、「再現可能な科学的知の条件とは何か」という科学哲学的問題に対し、実証的かつ規範的な回答を与えることを目的とする。
✅ 研究計画・方法
- 再現性危機の構造的要因の整理(文献レビュー+STS的視点)
複数分野における再現性危機に関する文献(例:Open Science Collaboration 2015)をもとに、統計的手法・データ公開・オーサーシップ・出版バイアスといった構造的要因を体系的に整理し、AIの導入によって新たに生じる可能性のある問題と比較する。
- 生成AIを用いた研究実践の調査(事例研究)
ChatGPTや生成AIツールを用いて分析・執筆されたプレプリントや公開論文を収集し、プロンプト・モデル設定・コードの有無・公開データの有無などを精査。これらの論文の再現可能性を、第三者による検証を通じて評価する。
- AI生成物に対する再現性指標の設計と実装
生成AIによる分析・執筆プロセスの透明性(例:プロンプトの開示、モデルバージョンの記録、コード・データの共有)を基に、再現性のためのメタデータ設計指針を提案し、再現性担保の制度設計に関する示唆を得る。
✅ 先行研究との差異と独創性・着想の経緯
再現性危機に関する研究は、心理学・医学・統計学などで蓄積されてきたが、生成AIという「新たな知の媒介装置」が再現性に与える影響に正面から取り組んだ研究は皆無に等しい。
本研究の独創性は、「AIが再現性を高めるのか、逆に曖昧にするのか」という問いを、実際の生成AIによる研究実践に即して検証し、科学的知の新たな条件を定式化する点にある。また、哲学的・社会的視点と情報技術的アプローチを統合することで、単なる技術論を超えた枠組みを提供することができる。
本テーマは、大学の研究演習でChatGPTを活用した分析の再現を試みた際、「同じプロンプトでも結果が揺らぐ」という経験から着想を得た。これが、「生成AIの科学的信頼性とは何か」という根源的問いへと発展した。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究は、AIを利用した科学実践において、「何が再現可能な知として認められるのか」という新たな規範を構築するものである。これは、科学的方法論・出版倫理・研究データ管理といった制度設計の基礎となる視座を提供する。
また、再現性を高めるAI活用法に関する提案は、Open ScienceやResponsible AIの実現にも資する。学術界・教育界におけるAIリテラシー育成の基盤形成にも波及効果が見込まれる。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私は、科学哲学・研究倫理・情報社会論に関する幅広い文献知識と、Python・Rを用いた分析技術の両面を習得してきた。特に、データ再現性に関する講義・演習に主体的に取り組み、GitHubやJupyter Notebookを用いた解析記録・再現可能なレポート作成にも慣れている。
2024年度には学内研究倫理コンペティションにて最優秀賞を受賞し、生成AIを利用したデータ分析の再現性に関するプレゼンテーションを行った。今後は、個別の技術論を越え、科学知の条件そのものを問い直す学際的研究へと発展させたいと考えている。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、科学技術と社会の関係に強い問題意識を持ち、とりわけ生成AIが科学研究の信頼性に与える影響について、極めて独創的かつ着実に研究を進めている学生です。
彼(彼女)は、調査設計・文献分析・数理的視点・ツール実装のすべてを一貫して自力でこなし、研究倫理・科学哲学・情報科学を架橋する思考力を有しています。今回の研究課題は、科学方法論・再現性・AI倫理の交差点に位置するものであり、学術的意義と社会的意義の双方において非常に高いと評価できます。
以上の理由から、〇〇〇〇君(さん)を特別研究員(DC1)として強く推薦いたします。
生成AI時代における査読制度の再構築に関する実証的・制度的研究:知の信頼性を担保する新たなモデルの設計
以下に、**「生成AIの登場が査読制度に与える影響と再構築の可能性」**をテーマとした、日本学術振興会特別研究員(DC1)申請書の架空記入例を提示します。科学技術社会論(STS)・情報倫理・科学コミュニケーションの観点を踏まえた、現代的かつ高い社会的関心を持つテーマ設定です。
✅ 研究課題名
生成AI時代における査読制度の再構築に関する実証的・制度的研究:知の信頼性を担保する新たなモデルの設計
✅ 研究目的および学術的背景
査読(peer review)は、近代科学における知の信頼性を保証する根幹的制度として発展してきた。従来、査読は専門家による人力での評価に支えられていたが、論文数の爆発的増加・査読者不足・査読の質のばらつきなど、制度疲労が各所で指摘されている。
このような背景の中、近年は大規模言語モデル(ChatGPT など)による自動査読支援ツールの導入が注目を集めている。実際、すでに論文ジャーナルやプリントサーバ上でAIによるレビュー補助の実験的運用が進んでおり、査読コメント生成・文章の明確化提案・論拠の確認支援などの機能が試みられている。
しかし一方で、「AIによる査読の正当性」「バイアス強化の危険性」「評価の責任主体」など、根本的な規範的・制度的課題が未整理のまま残されている。
本研究では、生成AIが査読制度に与える構造的影響を多角的に分析し、AIと人間の協働による新たな査読モデルの可能性を提示することを目的とする。
✅ 研究計画・方法
- 査読制度の現状と課題の整理(文献・制度分析)
主要学術分野における査読制度の歴史的変遷・現在の運用形態(ブラインド型・オープン型など)・査読の質と負担感に関する調査報告をレビューし、構造的課題を明確化する。
- 生成AIの査読支援利用に関する実態調査(アンケート・インタビュー)
研究者(査読者・著者)を対象に、生成AIを用いた査読補助の実態、利用経験、倫理的懸念などに関する調査を実施。査読過程におけるAI支援の有効性と問題点を定性的・定量的に分析する。
- AI+人間によるハイブリッド査読モデルの試設計と評価
AIによる初期スクリーニング+人間による最終判断といった段階的査読、あるいはAIによる透明な根拠提示型レビューといった代替案を構築し、既存制度との比較評価を行う。プロトタイプを用いた模擬査読ワークショップも検討する。
✅ 先行研究との差異と独創性・着想の経緯
査読制度に関する従来研究は、主にオープン化・匿名性・報酬制度など「人間同士の関係性」に焦点を当ててきた。一方、AIという「非人格的評価者」の登場によって、査読そのものの規範的意味が変容しつつあることへの本格的な分析はほとんど存在しない。
本研究の独創性は、査読を「社会的に知を承認する制度」として捉えたうえで、その構造がAI導入によってどう再編され得るかを、理論・制度・実践の3側面から同時に検討する点にある。単なる技術活用論ではなく、知の正当性の根拠を問い直す試みである。
着想の契機は、査読に参加した際に感じた「査読者としての判断の不安」と、「AIに意見を尋ねたくなる衝動」の間にある緊張だった。この経験から、査読の権威性とその基盤への関心が芽生えた。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究は、生成AI時代において科学的知を「誰が」「どのように」正当化するかという根本的な問題に取り組むものであり、研究倫理・科学政策・出版制度改革に関わる複数の領域に横断的に貢献する。
さらに、AIと人間の協働による査読モデルは、ジャーナル編集部・研究機関・助成審査機関等にとって、質と効率性の両立を可能にする制度的指針として活用可能であり、科学知の社会的信頼を回復・強化するための手段としても期待される。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私は学部時代より、科学コミュニケーション・学術出版制度・研究倫理に関心を持ち、査読制度の運用に関する比較制度分析や、オープンサイエンス運動に関する調査研究を行ってきた。これまでに学術雑誌の編集委員補助業務にも従事し、査読実務の実態を体験的に理解している。
また、Pythonを用いた自然言語処理やテキストマイニングの技術を活かし、AIによる査読支援コメントの分析や分類、信頼性スコアの算出なども実施可能である。これらの知見を融合し、科学制度の再構築に寄与する研究を主体的に進めていきたい。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、学術コミュニケーションと情報技術の融合に強い関心を持ち、とりわけ査読制度の構造的課題に着目し、これをAIの技術的展開と接続するという非常に現代的な問題設定を行っています。
彼(彼女)は、科学哲学的・制度論的な視点と、自然言語処理やツール分析といった実証的技法を併せ持ち、広い視野と実行力を有しています。本研究課題は、科学的信頼の新しい担保機構を考案するという点で大きな学術的意義があり、本人の能力に照らして十分に実現可能と考えます。
以上の理由から、〇〇〇〇君(さん)を特別研究員(DC1)として強く推薦いたします。
このテーマは、「生成AIの実用化が進む中で、科学知の承認メカニズムをいかに保つか」という現代的かつ哲学的な関心に根差しています。
多様な交通状況に対応可能な自動運転車のためのリスク認識型行動計画アルゴリズムの開発
以下に、日本学術振興会特別研究員(DC1)申請書の形式に則った**自動運転分野の記入例(架空)**を提示いたします。研究の独創性、実現可能性、社会的意義が伝わるよう丁寧に記述しています。
✅ 研究課題名
多様な交通状況に対応可能な自動運転車のためのリスク認識型行動計画アルゴリズムの開発
✅ 研究目的および学術的背景
自動運転技術は近年急速に発展しているが、都市部や混雑環境のような多様かつ動的な交通状況においては、依然として安全性と柔軟性の両立が困難である。現行の多くのシステムは、あらかじめ想定された状況においては高い性能を発揮する一方で、予測困難な交通主体(例:急に飛び出す歩行者、不規則に走行する自転車)への対応には限界がある。
本研究では、自動運転車が周囲の交通状況の「リスク」を認識・定量化し、そのリスクレベルに応じた動作計画を行うアルゴリズムを開発する。従来の行動計画が「安全距離」や「交通規則」に基づく静的判断であったのに対し、本研究では確率論的にリスクを扱い、柔軟かつ適応的に行動選択を行う点に新規性がある。
✅ 研究計画・方法
- リスク推定モジュールの構築
周囲の車両・歩行者の挙動履歴をもとに、将来の移動経路を確率的に予測し、衝突・接触の可能性を定量的に評価する。Gaussian Process や Conditional Variational Autoencoder (CVAE) を用いて不確実性を扱うモデルを構築する。
- リスク認識型行動計画の設計
リスク推定結果をもとに、自車の走行軌道を最適化する行動計画アルゴリズムを開発する。Cost Function にリスク項を導入した Model Predictive Control(MPC)やDeep Reinforcement Learning(例:Soft Actor-Critic)を用いる。
- 都市交通環境における評価
CARLAシミュレータ上で都市環境を再現し、歩行者密度・交通密度などを変化させた条件下で提案手法の性能を評価する。将来的には実機プラットフォーム(小型自動運転車両)への実装も視野に入れる。
✅ 先行研究との差異と独創性・着想の経緯
自動運転に関する既存研究の多くは、「最適経路計画」や「交通規則順守」に基づく行動決定が主であり、周囲の不確実な挙動を動的にリスクとして扱う手法は少ない。近年、行動予測の精度は向上しているが、それを「行動選択」に有効活用している事例は限定的である。
本研究の独創性は、周囲の行動を「確率的に予測→リスクとして定量化→計画に反映」する一連の統合アルゴリズムを設計する点にある。また、リスクの明示的な扱いにより、「安全性」と「過剰な保守性」のバランスをとった行動を可能とする。
着想の背景には、大学2年次に参加した自動運転の国際ハッカソンで、「人の少ない交差点では慎重すぎる運転がかえって危険を招く」という現象を観察した経験がある。静的なルールではなく、動的な状況理解が必要だと強く感じたことが研究の出発点である。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究は、現実世界に近い動的な交通環境において、より現実的で実用的な自動運転制御を可能にするアルゴリズムの基盤を提供するものである。安全性を確保しつつ、交通の流れを妨げない柔軟な運転制御を実現できれば、都市部での自動運転の社会受容性が飛躍的に高まる。
また、リスクを定量化して行動計画に反映させるという手法は、自動運転以外にも災害対応ロボット、無人搬送車(AGV)、ドローン制御などに広く応用可能であり、ロボティクス全体に波及効果があると考えられる。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私は大学3年次より自動運転システム研究室に所属し、深層学習を用いた行動予測モデルや、LiDARとカメラを用いたセンサ融合処理の研究に従事してきた。特に、CARLAを用いた仮想環境での学習・評価系の構築、およびROSによるセンサデータ処理・制御指令の送信など、システム全体を一貫して扱える経験を積んでいる。
2024年度にはIEEE ITSC(Intelligent Transportation Systems Conference)で研究成果を発表し、査読付き論文として現在投稿準備中である。以上のような経験と環境を活かし、本研究課題を独立して遂行する自信がある。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、ロボティクスと人工知能の融合に関心を持ち、特に自動運転における行動計画に関して高い専門性と技術力を有している学生です。本人は単なるモデル構築にとどまらず、実環境への応用まで見据えた問題設定ができ、学部学生としては非常に優れた研究遂行能力を示しています。
本研究課題は、既存の自動運転アーキテクチャの限界を踏まえつつ、不確実性を定量的に取り扱うことでより実用的な制御を目指すものであり、学術的にも応用的にも意義が大きい。本人の熱意・技術・独創性を考慮し、特別研究員(DC1)として強く推薦いたします。
都市環境における自動運転車の安全・柔軟な行動計画を実現する認識―意思決定統合フレームワークの構築
以下に、**自動運転技術(知覚と意思決定の統合)**をテーマとした、日本学術振興会特別研究員(DC1)申請書の架空記入例を示します。実際の申請書作成の参考になるよう、専門性・独創性・実現可能性を意識した記述にしています。
✅ 研究課題名
都市環境における自動運転車の安全・柔軟な行動計画を実現する認識―意思決定統合フレームワークの構築
✅ 研究目的および学術的背景
自動運転車の社会実装が進む中、複雑で予測困難な都市環境において安全かつ柔軟に走行できる制御系の構築は、依然として大きな課題である。歩行者・自転車・他車両といった多様な交通主体の不確実な動きを捉え、それに応じた適切な行動を即時に選択する能力が求められている。
本研究の目的は、都市環境において自動運転車が周囲の動的状況をリアルタイムに理解し、安全かつ柔軟に行動計画を立案・実行するための知覚―意思決定の統合フレームワークを開発することである。具体的には、3Dセンシングによる周辺状況の高精度認識、深層強化学習による行動決定、さらに両者を接続する不確実性考慮型情報統合モジュールの構築を目指す。
✅ 研究計画・方法
- 都市環境向け3D知覚モデルの構築
LiDARやカメラから得られるマルチモーダルなセンサデータを用いて、歩行者・車両・インフラなどの物体検出と追跡を行う。特に、点群と画像の融合による精密な3Dセマンティックマッピングを実装する。
- 不確実性伝搬を考慮した意思決定支援モジュールの設計
認識段階で生じる不確実性(例:センサノイズ、死角など)を、行動選択時に考慮できるよう、Bayesian Deep Learning や Monte Carlo Dropout を導入した状態推定モデルを構築する。
- 強化学習による行動選択アルゴリズムの開発
Deep Reinforcement Learning(例:SAC、TD3)を用いて、自車の動作計画をオンラインで最適化する。仮想環境(CARLAシミュレータ)と実車プラットフォームの両方で段階的に評価を行う。
✅ 先行研究との差異と独創性・着想の経緯
これまでの研究では、認識と行動計画をモジュール分離して設計するアーキテクチャが主流であり、認識誤差が行動に直接影響することが問題視されてきた。また、行動決定アルゴリズムにおける不確実性考慮は十分でない。
本研究の独創性は、センサ情報の不確実性を定量的に扱いながら、リアルタイムで行動を最適化する認識―意思決定統合型の新たな制御フレームワークを提案する点にある。また、シミュレータと実環境の双方で学習・評価を行うことで、実装可能性の高いモデルを目指す。
この着想は、学部時代に海外で自動運転車の交通事故に関する報道に接したことが契機となった。原因が「認識精度不足」と「保守的すぎる判断」であったことに注目し、安全性と柔軟性の両立の難しさに問題意識を持ったことが出発点である。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究により、自動運転車が複雑な都市環境下で安全にかつ自然に走行するための技術的基盤を提供できる。特に、高齢者や子どもといった予測困難な存在との共存を実現する上で、行動の柔軟性と予測可能性を高める意義は大きい。
また、不確実性を明示的に取り扱う枠組みは、災害対応ロボットや無人搬送システム(AGV)など、他のモバイルロボティクス分野にも応用可能であり、実時間意思決定アルゴリズムの一般化に資する波及効果が期待できる。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私は大学3年次より知能制御工学研究室に所属し、CARLAやAutowareを用いた自動運転シミュレーション環境の構築、深層強化学習(DQN, PPO)を用いた経路計画の研究を行ってきた。また、ROS環境下でのセンサ統合処理やLiDAR点群解析などの技術も習得済みである。
研究成果の一部は、2024年度のIEEE Intelligent Vehicles Symposium(IV)にてポスター発表を行った。また、Open Source プロジェクトへのコード提供や、他大学との共同実験にも積極的に参加している。
以上のような経験を基に、本研究課題についても、計画から実装・検証までを主体的に遂行する準備が整っていると自負している。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、大学3年次より自動運転技術に関心を持ち、深層学習を用いた経路計画とセンサフュージョンの研究に継続的に取り組んでいる学生である。彼(彼女)は、シミュレーション環境の立ち上げから実装・デバッグまでを自ら行う実行力と粘り強さを備えており、既に大学院レベルの研究遂行能力を有している。
今回の研究課題は、自動運転分野の主要課題である「認識と意思決定の接続」に取り組むものであり、非常にタイムリーかつ学術的意義が大きい。本人の技術力・論理性・責任感に照らしても、特別研究員として採用されるに十分ふさわしい資質を備えている。
以上の理由から、私は〇〇君(さん)を特別研究員(DC1)として強く推薦する。
人間の非言語的シグナルに基づく協調行動を実現するロボットの行動生成モデルの開発
以下に、**ロボティクス分野(認知ロボティクス・ヒューマンインタラクション)**をテーマとした、日本学術振興会特別研究員(DC1)申請書の架空記入例を提示いたします。
✅ 研究課題名
人間の非言語的シグナルに基づく協調行動を実現するロボットの行動生成モデルの開発
✅ 研究目的および学術的背景
近年、ロボットが工場や倉庫だけでなく、医療・介護・教育・接客といった人間中心の環境で活用される機会が急増している。こうした環境では、ロボットが人間と自然に協調して行動することが求められ、言語のみならず、視線・ジェスチャー・身体の向きといった非言語的シグナルを的確に理解し応答する能力が必要とされる。
本研究の目的は、人間の非言語的行動をリアルタイムに認識し、それに応じてロボットが適切な行動を生成するモデルを構築することである。従来の研究では、言語による命令指示に対するロボットの反応が主であったが、人間同士のような暗黙的な協調を実現するには、より繊細な認知・行動生成機構が必要である。
本研究では、ヒトの行動データを基にしたマルチモーダル認識モデルと、行動決定の強化学習モデルを統合し、対人協調行動におけるロボットの自然な応答行動の生成を目指す。
✅ 研究計画・方法
- マルチモーダル非言語行動データの収集と分析
ヒト同士の共同作業(例:物体の受け渡し、共同探索)を対象に、視線・顔向き・手の動き・体幹の向きといった非言語的情報をRGB-Dカメラや視線追跡装置を用いて収集・構造化する。
- 非言語的意図推定モデルの構築
収集データを基に、TransformerやGraph Neural Network(GNN)を活用し、複数モダリティから人間の意図(例:注視対象、次の行動予測)をリアルタイムで推定するモデルを構築する。
- ロボットの行動生成モデルの学習
推定された人間の意図に応じて、ロボットが柔軟に行動を決定できるよう、強化学習(例:Deep Q-Network, PPO)を用いた行動生成モデルを訓練する。人間との対話や共同作業の場面において、自然で破綻のない振る舞いができるかを実証的に検証する。
✅ 先行研究との差異と独創性、着想の経緯
これまでのロボットの協調行動研究は、音声命令や明示的なジェスチャーなど、分かりやすい信号に依存していた。一方、人間同士の共同作業においては、視線や姿勢といった非言語的かつ曖昧なシグナルの解釈が不可欠である。
本研究の独創性は、非言語的インタラクションの暗黙的意味を学習し、それに応じた自然な行動を自律的に生成するロボット行動モデルを構築する点にある。また、GNNやマルチモーダル注意機構など、近年注目される深層学習技術を応用することで、複雑な対人インタラクションを処理可能な枠組みを提供する。
着想のきっかけは、学部時代に高齢者介護ロボットのデモを見学した際、声掛けには反応するが、視線や手振りには対応できないロボットに違和感を覚えた経験による。人間と共存するロボットには、より「人間らしい文脈理解」が必要だと痛感し、このテーマに至った。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究は、人間との協調行動を重視したロボットの行動知能の設計に寄与するものであり、介護・接客・教育など多様な分野での応用が期待できる。また、ヒューマン・ロボット・インタラクション(HRI)の設計原理に新たな視点を提供する。
さらに、視線・身体動作といった人間特有の行動パターンに着目することで、認知科学や心理学分野との学際的連携も見込まれる。人間に対する理解を深めるロボティクスは、真に人間社会に溶け込む技術の基盤となると考えている。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私は学部3年次より知能ロボティクス研究室に所属し、視覚認識と行動計画に関する研究に取り組んできた。これまでに、RGB-Dセンサを用いた物体認識、ROSを利用した移動ロボット制御、強化学習による動作最適化の技術を習得した。
研究成果の一部は、2024年度の日本ロボット学会学術講演会にて口頭発表を行い、審査員より「行動モデルの工夫が際立っている」とのコメントを頂いた。また、研究室内でのディスカッションや輪読会を通じて、最新の論文理解・実装力の向上に努めている。
今後は、非言語的協調行動という未踏領域に挑戦し、将来的には「人と共に働くロボット」の実現に貢献したいと考えている。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、認知的ロボティクスに高い関心を持ち、学部時代から深層学習や強化学習を駆使したロボット知能の設計に積極的に取り組んできた学生です。彼(彼女)は実験計画からアルゴリズム実装、評価までを一貫して自ら進めることができ、非常に高い自立性を備えています。
特に、HRIの文脈で非言語的情報の処理に挑む今回の課題は、申請者のこれまでの経験と関心に非常に合致しており、学術的にも大きな貢献が期待されます。研究室にはセンサ環境・プラットフォーム・共同研究体制が整っており、研究遂行上の制約もありません。
以上の理由から、私は〇〇君(さん)を特別研究員(DC1)として強く推薦いたします。
言語モデルにおける事実性推論の自動評価手法の開発とその応用
以下に、**コンピュータサイエンス分野(人工知能・自然言語処理)**をテーマとした、日本学術振興会特別研究員(DC1)申請書の架空記入例を示します。構成・言葉遣いは学振書類の慣例に即して整えています。
✅ 研究課題名
言語モデルにおける事実性推論の自動評価手法の開発とその応用
✅ 研究目的および学術的背景
近年、大規模言語モデル(LLMs)は、対話生成・要約・質問応答など多様な自然言語処理タスクで高精度な出力を示している。しかし、これらの出力にはしばしば「もっともらしい誤情報(hallucination)」が含まれており、特に医療や法務など高信頼性が要求される分野では深刻な問題となっている。
本研究の目的は、言語モデルの生成結果が事実に即しているか(=事実性/faithfulness)を自動で評価する手法を開発することである。従来のBLEUやROUGEといった表面的な一致度指標では、意味的な正確さを保証できないため、知識ベースや検索エンジンと連携させた評価指標の設計が求められている。
本研究では、①文脈と外部知識の整合性に基づいた事実性スコアの設計、②日本語・英語に対応した多言語評価ベンチマークの構築、③言語モデルのトレーニング・評価への統合という3段階での実現を目指す。
✅ 研究計画・方法
- 知識整合性に基づく事実性スコアの設計
生成文と元文(例:要約元のニュース記事)との関係を意味的に評価するため、Open-domain QA や自然言語推論(NLI)の手法を活用する。また、外部知識としてWikipediaやPubMedなどの知識ベースを用い、文と知識の一致度を自動計算する評価モジュールを構築する。
- 多言語ベンチマークの構築
日本語・英語のニュース要約・質問応答データセットを基に、専門家による事実性アノテーションを施した評価用データセットを作成する。研究コミュニティで共有可能な形式で整備し、他のモデルとの比較検証を可能にする。
- 言語モデルの評価・改善への応用
開発した事実性スコアを学習の損失関数に組み込み、事実性を強化した新たな生成モデルの訓練を行う。また、評価指標として実運用環境における信頼性向上効果を実証する。
✅ 先行研究との差異と独創性・着想の経緯
従来の自然言語生成評価手法はBLEUやROUGEなどn-gramの一致度に依存していたが、事実性という観点からは不十分である。近年、GPT-4やClaudeなど高性能なLLMの登場により、より文脈的・意味的な評価が求められている。
本研究の独創性は、言語モデルの出力に対して検索ベース・推論ベースの知識整合性指標を導入し、事実性を自動で検出・スコア化する点にある。単なる分類モデルではなく、生成文全体にスコアを割り振ることで、実運用でのフィードバックループにも応用可能となる。
この着想は、学部時代にChatGPTの出力の中に、明らかに不正確な情報が含まれていた経験に基づいている。それを契機に「AIが生成した情報の真偽をどう保証するか」という問題に関心を持ち、本研究計画の構想へと至った。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究は、自然言語生成の品質評価という基礎的課題に取り組むものであり、言語モデルの社会実装における信頼性向上に直結する意義を有する。また、医療や教育、行政文書の要約など実用的場面での誤情報抑制にも貢献しうる。
さらに、日本語を含む多言語への応用を視野に入れることで、日本語LLMの性能評価基盤の確立にも寄与できる。将来的には、出力の正確性に基づいたLLMのランキング基準や安全性基準の設計にも波及効果が期待される。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私は大学3年次より自然言語処理研究室に所属し、Transformerベースの生成モデルの学習と評価に関する研究に取り組んできた。特に、BARTやT5を用いた自動要約モデルの開発と、日本語データセットに対するファインチューニングに従事した経験がある。
また、PythonおよびPyTorchを用いたモデル実装や、GPUクラスタでの大規模データ処理にも精通しており、scikit-learnやHuggingFace Transformersといった主要ライブラリの活用経験も豊富である。
研究成果の一部は、2024年の言語処理学会年次大会にてポスター発表を行ったほか、共同研究として学会誌への投稿準備も進めている。今後は、LLMの信頼性評価という重要課題に対し、自律的かつ継続的に取り組む所存である。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、自然言語処理に強い関心と探究心を持ち、大学3年次より私の研究室で研究活動に励んでいる学生です。生成モデルの原理に加え、GPU計算環境の扱いにも精通し、技術的理解と応用力を兼ね備えています。
中でも注目すべきは、研究課題の社会的意義を明確に意識し、それに基づいた問題設定ができる点です。既存モデルの精度向上だけでなく、「信頼できるAI出力とは何か」という本質的な問いに立ち向かおうとする姿勢は、将来の研究者として極めて有望です。
今回の研究課題は、AI社会実装に不可欠な出力の事実性保証に取り組むものであり、本人の知識・技術・意欲をもってすれば十分に遂行可能と確信しております。私は〇〇君(さん)を特別研究員(DC1)として強く推薦いたします。
腸内常在菌に応答する自然免疫系の恒常性維持機構の解明
以下に、免疫学分野のテーマに基づいた、日本学術振興会特別研究員(DC1)申請書の例文を提示します。内容・言葉遣いは、実際の申請書にふさわしいよう整えてあります。
✅ 研究課題名
腸内常在菌に応答する自然免疫系の恒常性維持機構の解明
✅ 研究目的および学術的背景
ヒトの腸管は、膨大な数の常在細菌と接する一方で、病原体からの防御機構も兼ね備える特殊な免疫環境である。このような環境下で、自然免疫系は、過剰な炎症を抑制しつつも迅速な応答を可能にする高度な調節機構を有している。
本研究では、腸内常在菌に対する自然免疫系の制御機構を明らかにすることを目的とする。特に、腸管上皮細胞と自然免疫細胞とのクロストークに着目し、その分子基盤を明らかにすることで、炎症性腸疾患(IBD)などの疾患発症メカニズムの解明に資する基礎的知見を提供したいと考えている。
✅ 研究計画・方法
- 動物モデルと常在菌の操作
無菌マウスおよび特定病原菌不在(SPF)マウスを用い、特定の常在菌を単独または複数菌種で再構築したモデルを作製し、自然免疫系の応答を比較する。
- 自然免疫応答の解析
主に腸管のパイエル板および粘膜固有層のマクロファージ、樹状細胞、ILC(innate lymphoid cell)に焦点を当て、フローサイトメトリーおよびscRNA-seqを用いて免疫細胞の表現型と機能を解析する。
- 腸管上皮細胞との相互作用の検証
オルガノイド培養系を用いて、腸管上皮と免疫細胞の相互作用を再構築し、TLR(Toll-like receptor)やNLR(NOD-like receptor)経路の関与を検証する。
✅ 先行研究との差異と独創性、着想の経緯
これまでの研究では、腸内常在菌による免疫系の「教育」機構が注目されてきたが、多くは獲得免疫系に焦点を当てており、自然免疫系、とくにILCやマクロファージなどの機能的多様性については未解明の点が多い。
本研究の独創性は、自然免疫系が常在菌に対して“どのようにして過剰応答を回避し、恒常性を維持しているか”という問いに、オルガノイド培養や単一細胞解析などの先端技術を用いて挑む点にある。
本テーマに着想したきっかけは、学部時代にIBD患者の症例について学んだ際、免疫系の過剰応答が疾患の一因となるという事実に衝撃を受けたことである。その後、研究室で腸管免疫に関する基礎研究に従事する中で、自然免疫細胞の可塑性と複雑な制御機構の魅力に惹かれ、本研究計画の立案に至った。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究は、自然免疫系による恒常性維持機構の理解を深めるものであり、腸内環境と免疫系の相互作用に関する新たな概念の確立につながる可能性がある。また、IBDや自己免疫疾患において、常在菌との不適切な応答が病態進行に関与することから、新たな予防・治療標的の同定にも寄与しうる。
さらに、自然免疫と腸内細菌とのバランス制御機構を明らかにすることは、ワクチンアジュバント開発やバイオセラピューティクス開発への応用も期待できる。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私はこれまでに、腸管免疫を専門とする研究室において、無菌マウスの管理、フローサイトメトリーによる免疫細胞解析、オルガノイド培養などの実験技術を習得してきた。3年次には特別研究実習にてミニプロジェクトを担当し、研究成果を第70回日本免疫学会総会にて発表した実績がある。
また、定期的な研究進捗報告会や英文論文の抄読会を通じて、研究計画の立案力や文献考察力を磨いてきた。こうした経験を通じて、自ら課題を発見し、実験を設計し、結果を解釈するという研究プロセスを自立して進める力を養ってきた。
今後は、大学院進学後に本研究をさらに発展させ、国際的にも通用する研究成果を発信したいと考えている。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、学部3年次より私の研究室に所属し、腸管免疫の研究に積極的に取り組んできました。非常に熱意と探究心に富み、短期間でフローサイトメトリーや無菌マウスの取り扱いといった高度な実験技術を習得しました。
特に特筆すべきは、与えられた課題に対して深く掘り下げ、自ら実験系を提案・構築する力がある点です。研究室内のディスカッションでも的確な意見を述べ、既に大学院生レベルの論理的思考力とプレゼンテーション能力を有しています。
今回申請された研究課題は、腸内常在菌と自然免疫系のクロストークという極めて重要かつ未解明のテーマに取り組むものであり、学術的意義と将来性に富んでいます。本人の能力と当研究室の環境をもってすれば、十分に遂行可能であると確信しており、私は〇〇君(さん)を特別研究員(DC1)として強く推薦いたします。
環境ストレス応答における植物転写因子ネットワークの動的制御機構の解明
以下に、日本学術振興会特別研究員(DC1)申請書の**植物学分野(植物環境応答・遺伝子発現制御)**に関する架空の記入例を示します。内容は申請書のフォーマットに準じており、専門性・独創性・社会的意義がバランスよく伝わるよう工夫しています。
✅ 研究課題名
環境ストレス応答における植物転写因子ネットワークの動的制御機構の解明
✅ 研究目的および学術的背景
植物は移動能力を持たないため、乾燥・塩害・高温などの環境ストレスに対して、発生・代謝・遺伝子発現レベルで多様な適応応答を行う。近年の研究により、ストレス応答に関与する主要な転写因子群(例:DREB, NAC, bZIPファミリー)や、それらの下流遺伝子の一部が明らかになってきた。
しかし、それらの転写因子が時間的・空間的にどのように協調してストレス応答を制御しているのかについては、十分に理解されていない。特に、複数の転写因子が同一のプロモーターに結合して相互に作用し合う動的な制御ネットワークの全体像は未解明である。
本研究は、乾燥ストレス応答をモデル系とし、転写因子ネットワークの構造とその時間的制御機構を多角的に解析することを目的とする。植物の環境応答メカニズムの基盤を解明することで、将来的にはストレス耐性作物の分子設計にも貢献することが期待される。
✅ 研究計画・方法
- 主要転写因子の網羅的発現解析(RNA-seq)
乾燥処理を行ったモデル植物(シロイヌナズナ)から、時間経過ごとのサンプルを収集し、RNA-seq解析を行う。主な転写因子群の誘導タイミングを比較することで、ストレス応答における制御階層を明らかにする。
- クロマチン免疫沈降(ChIP-seq)による標的遺伝子の同定
代表的なストレス応答性転写因子(例:DREB2A, ABF3)にタグを付加したトランスジェニック植物を用い、乾燥処理前後でのChIP-seqを実施する。複数の転写因子による標的遺伝子の共有・排他的制御の関係を明らかにする。
- 転写因子間相互作用の検証(Y2H・BiFC)
発現タイミングや標的遺伝子が重なる転写因子同士について、酵母ツーハイブリッド法およびBiFCを用いて直接的な相互作用の有無を調べる。
- 数学的モデルによる応答ダイナミクスの再構成
発現・結合・相互作用の時間的データをもとに、制御ネットワークのダイナミクスをシステム生物学的アプローチでモデル化する。
✅ 先行研究との差異と独創性・着想の経緯
これまでの多くの研究は、個々の転写因子の機能解明にとどまり、複数の転写因子が協調・拮抗的に働くネットワーク構造や、その時間的推移の定量的理解には至っていない。
本研究の独創性は、**「複数因子による多層制御構造」+「時系列変化」+「相互作用」**という複数の次元から、ストレス応答の制御メカニズムを統合的に解析する点にある。加えて、これらの情報を数学モデル化することで、複雑な制御構造の動作原理を形式的に記述・予測可能とする。
このテーマは、学部3年次の植物生理学実習で、わずかな乾燥処理によって形態が著しく変化する様子を目にしたことに起因する。植物の柔軟な応答力の背景にある「制御の仕組み」への興味が、研究の原点である。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究は、環境ストレス応答における植物の遺伝子制御の基本原理を明らかにすることにより、植物科学の基盤的理解を深める意義を持つ。また、耐乾燥性をはじめとするストレス耐性作物の品種開発において、転写制御ネットワークという新たな分子育種ターゲットの提案にもつながる。
さらに、得られた動的ネットワークモデルは、他の植物種や異なるストレス条件(塩害・寒冷)への応用が期待される。すなわち、応答予測・遺伝子選抜・バイオインフォマティクスとの連携による農業・環境分野への波及効果も大きい。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私はこれまで、植物のストレス応答に関する分子生物学的実験に主体的に取り組んできた。具体的には、RT-qPCRによる遺伝子発現解析、トランスジェニック植物の作製、免疫染色、および共焦点顕微鏡を用いた局在観察を習得済みである。
また、RNA-seq解析においてはR/Bioconductor環境下でのデータ処理や、ChIP-seqデータのマッピングとピーク検出も経験しており、バイオインフォマティクスの基礎的スキルを有している。
研究成果の一部は、2024年度日本植物学会大会にて発表を行い、同分野の研究者との活発な議論を経験した。今後は、これらの知識・技術を基盤として、本研究課題を自立的に遂行する覚悟である。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、学部3年次より当研究室で植物の環境応答に関する研究に取り組んでいる学生であり、高い実験技術と論理的思考力を兼ね備えた非常に優秀な人材である。
本人は遺伝子発現解析やシロイヌナズナのトランスジェニック系統の構築などを一貫して自ら遂行しており、研究の設計からデータ解釈までを独立して行える能力を有している。また、研究への関心が非常に高く、学会参加や論文抄読を通じて、常に新しい知識の吸収に努めている。
今回の研究課題は、植物の環境ストレス応答における転写制御ネットワークの全体像を明らかにするものであり、学術的にも応用的にも極めて重要なテーマであると認識している。本人の能力と意欲をもってすれば、特別研究員として十分な成果を挙げられると確信しており、強く推薦する。
植物の形態形成におけるホルモン輸送と成長ダイナミクスの数理モデルの構築
以下に、**植物学における数理モデル(成長・環境応答のモデリング)**をテーマとした、日本学術振興会特別研究員(DC1)申請書の架空記入例を示します。計算科学と植物生理の融合に主眼を置いた構成としています。
✅ 研究課題名
植物の形態形成におけるホルモン輸送と成長ダイナミクスの数理モデルの構築
✅ 研究目的および学術的背景
植物の成長と形態形成は、細胞レベルでの分裂・伸長、およびそれらを空間的に制御するホルモンの輸送・分布により制御されている。特にオーキシン(AUX)は、局所濃度により細胞の成 fate を制御する中心的な役割を果たしており、PIN輸送体による極性輸送によって空間分布が形成されることが知られている。
一方で、ホルモン分布と細胞の成長応答がどのように時間的・空間的に連関し、全体として組織や器官の形を生み出すかについては、依然として不明な点が多い。実験データの蓄積が進む一方で、定量的な数理モデルに基づく統合的理解は十分に進んでいない。
本研究では、オーキシンの極性輸送と細胞の成長応答を結合した数理モデルを構築し、植物の形態形成ダイナミクスを再現・予測することを目的とする。
✅ 研究計画・方法
- オーキシン輸送モデルの構築(PDEモデル)
細胞間を移動するオーキシンの濃度分布を、反応拡散方程式と極性輸送項を含む偏微分方程式(PDE)でモデル化する。輸送体の分布や方向性を時空間的にパラメータ化する。
- 細胞成長モデルとの結合
各細胞がホルモン濃度に応じて体積成長する仮定のもと、細胞壁の物理的変形を仮想2Dまたは3D細胞格子モデルで記述する。Growth Tensorや力学的相互作用を含めて記述し、オーキシン-成長連関を再現する。
- 数値シミュレーションとパラメータ推定
実験から得られたホルモン分布データおよび成長パターン(例:根端・葉原基)の時系列画像を基に、最適化アルゴリズム(例:MCMC、Bayesian inference)を用いてモデルのパラメータを推定する。
- モデルによる形態予測と実験検証
構築したモデルを用いて、オーキシン分布異常や輸送体変異体における成長予測を行い、既報の形態形成異常との整合性を確認する。さらに、予測される未報の現象について実験系との連携により検証を試みる。
✅ 先行研究との差異と独創性・着想の経緯
オーキシンの輸送とその空間分布については、局所的なホルモン濃度を記述するモデルが存在するが、細胞の成長や器官全体の形態変化とホルモン制御を結びつけた動的・連続的なモデルは限られている。
本研究の独創性は、ホルモン輸送・濃度勾配・細胞成長・形態変化という複数階層の現象を、反応拡散系と力学系を統合した数理モデルとして記述する点にある。これにより、形態形成過程を単なる観察対象から「予測可能な現象」へと昇華させることができる。
本テーマは、学部時代に植物の葉序形成に関する研究を調べた際、「螺旋配列」や「黄金比」といった美しいパターンが物理・数理モデルで再現できるという事実に感銘を受け、植物の形と成長の数理的理解に強い関心を抱いたことがきっかけである。
✅ 研究の意義・波及効果
本研究により、植物の成長と形態形成を支える基本原理を、数理的・定量的に記述できる枠組みが得られる。これは、単なる現象論的記述を超えた**「メカニズムの理解と未来予測の手段」**として、発生生物学・植物形態学に新しい視点をもたらす。
さらに、得られたモデルは、形態設計に応用可能な植物工学や、気候変動下での成長予測、あるいは植物の進化的戦略の解析にも波及可能であり、基礎から応用まで幅広い植物科学への貢献が期待される。
✅ 研究遂行能力に関する記述(本人記載)
私は植物発生学・形態形成の基礎を学ぶ一方、独学で常微分方程式・偏微分方程式・ベイズ推定法など数理モデリングに関する理論を学び、PythonおよびMATLABを用いた数値解析の訓練を行ってきた。
研究室では、オーキシン分布の蛍光顕微鏡画像の定量化、画像ベースの細胞成長追跡、簡易的なGrowth Modelの数値実装を担当し、数理的視点から実験結果を解釈する試みを行ってきた。
これまでに学会発表1件(2024年植物形態学会)、データ可視化・数式モデルの実装・データ同化の基礎技術を習得済みであり、今後は研究の高度化・統合化を図りつつ、自律的に研究を進める体制を整えている。
✅ 指導教員の推薦理由(様式2)
申請者〇〇〇〇君(さん)は、植物の発生・成長に対する深い関心を持ち、数理モデルという切り口から現象を捉えようとする、きわめて独創的な研究姿勢を有している学生です。
本人は実験観察だけでなく、定量的解析・モデル構築・数値計算という多面的なアプローチを意欲的に取り入れており、これまでに複数の独自モデルを構築・シミュレーションしています。理論と実験の架け橋として、研究室内でも重要な役割を果たしており、将来性ある若手研究者であると確信しています。
本研究課題は、形態形成の動力学的制御を統合的に記述するという、植物科学における重要かつ未解明の問題に取り組むものであり、強く特別研究員(DC1)として推薦いたします。