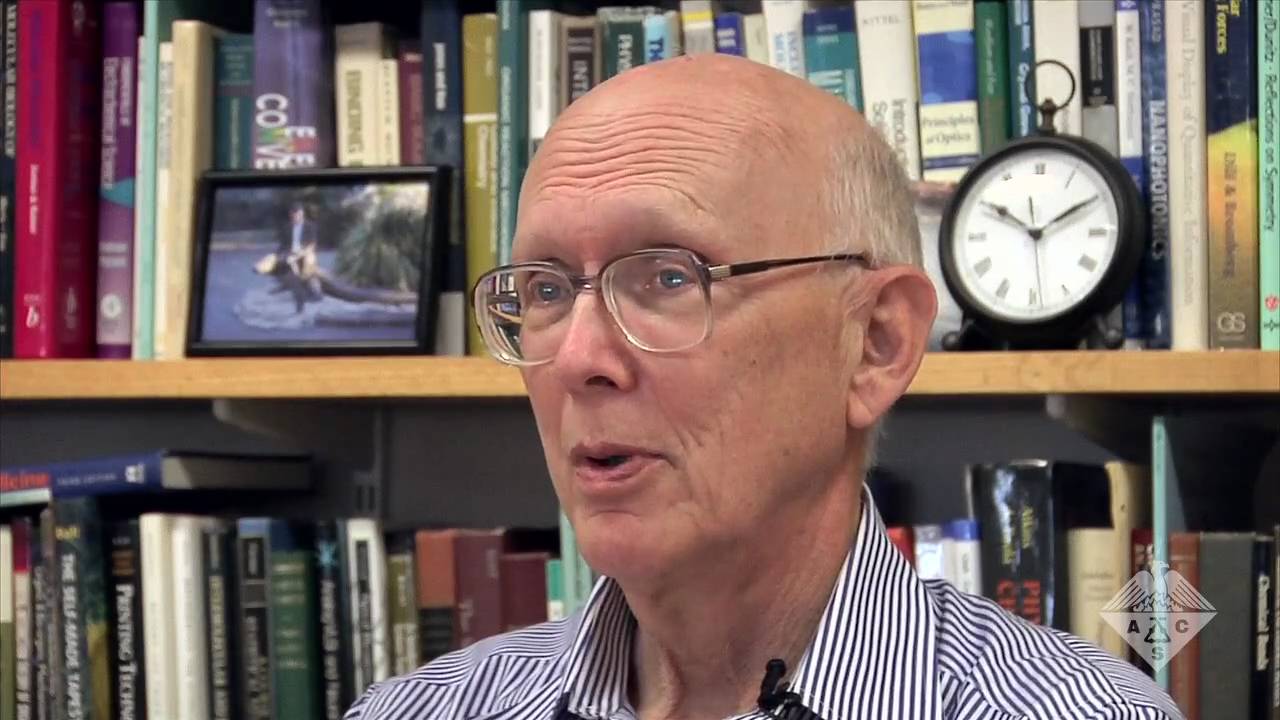大学院に進学した学生や新しいポスドクが、新しいラボでしばらくの間研究テーマを模索し、やがて面白そうでしかも自分にできそうなことを見つけて研究を始める。ボスもそれを認めて、やりたいようにやらせる。数年後、ラッキーなことにそれなりに実験データが溜まってきて、論文を書き始める。しかし、いざ書くとなると、なかなか筆が思うように進まない。それはなぜかというと、せっかく得られた実験結果から導き出せる結論があまりにも弱いから。こうなってしまうと、良い論文を出すことは困難です。
研究プロジェクトを一度始めてしまうと、研究分野にもよりますが数ヶ月、あるいは数年間、その研究を続けることになります。その努力が良い論文として結実しないことには、本人の研究者としてのキャリアが危ぶまれますし、ラボも停滞します。最終的なアウトプットの段階でこのような後悔をしないためには、どうすればいいのでしょうか?
良い科学研究論文を能率よくラボから出すための指針を、ハーバード大学の化学者、ホワイトサイズ教授が短いエッセイにまとめています。この文章はかなり有名で、既にいろいろなところで紹介されています。
これを書いたジョージ・ホワイトサイズ教授は、これまで950本以上の論文を書いており、1981年から1997年の間でもっともよく引用された 1,000人の科学者のうち、5位にランキングされている人であり、さらに2011年12月の時点で、現存する科学者の中で一番h指標が高い研究者なので す。ハーバード大学でMITを取り、同大学で教授になって、300人を超える学生と学者を指導してきました。(http://www.editage.jp/insights/a-3-page-guide-to-scientific-writing)
以下のサイトでは、日本語訳も紹介されています。
今回紹介する文献“Whitesides’ Group: Writing a Paper”では、世界一線級の化学者であるGeorge M. Whitesides教授が自ら、優れた論文執筆法を解説しています。具体的には『アウトライン法』――すなわち、始めに論文の枠組み(アウトライン)を作り、研究データの蓄積と同時並行して何度も修正を加えてゆく、実験データはその時々で補完、図表重視のアピールを心がけ、テキストを書くのは一番最後、という論文作成法――の提唱を通じ、研究のプロダクティビティ・時間効率の向上に効果的たる仕事術にも触れています。(http://www.chem-station.com/blog/2009/12/whitesides_group_writing_a_pa.html)
もともとAdvanced Materialsという学術誌に2004年に掲載されたものですが、このジャーナルのアクセスランキングでいまでも上位に入るほどの人気エッセイです。
英語の原文はこちら:Whitesides’ Group: Writing a Paper, Whitesides, G.M., Advanced Materials, 2004, 16, 1375-1377. (ラボのウェブサイト上のPDFリンク)。
ホワイトサイズ教授が論文執筆について語るインタビュー動画
Publishing Your Research 101 – Episode 1: How to Write a Paper to Communicate Your Research
参考
- Whitesides’ Group: Writing a Paper, Whitesides, G.M., Advanced Materials, 2004, 16, 1375-1377:ラボのウェブサイト上のPDFリンク
- Whitesides Research Group: Professor George M. Whitesides, Department of Chemistry and Chemical Biologym Harvard University:ホワイトサイズ教授の研究室ウェブサイト
- 化学者のつぶやき Whitesides’ Group: Writing a paper(Chem-Station 日本最大の化学ポータルサイト 2009年12月24日)
- 科学的文章を書くための3ページのガイド(editage Insights 2014年3月31日)
同じカテゴリーの記事一覧
- 科研費の採否はここで決まる!研究計画調書(申請書)の書き方~項目別実践的攻略ポイント~
- 蓮舫氏「2位じゃダメなんですか?」発言の真相:切り取られて作られた報道
- 科研費が採択されない人の特徴
- 論文を書き始めることができないんですけど?
- 科学論文で使える英語表現、語句、英単語
- 英語論文の書き方:文と文とをつなげる
- 利根川進博士のぶっちゃけ話:研究者として成功できた理由および成功戦略
- 東北大学の女性限定教授公募の波紋「教授って合コンサークルか何かなのか?」
- 数量化1類、数量化2類、数量化3類、林知己夫の数量化理論
- 大学教員を目指す公募戦士の戦い方、デキ公募という難敵の回避方法など
- 研究の行き詰まりを打開する18のアイデア
- 【科学英作文】useを使うかutilizeを使うか?使い分けの考え方
- 生命医科学研究領域の論文出版数で測った日本の大学の研究力ランキング
- 科研費に採択されるための教科書と副読本、厳選5冊
- ラボは何時間労働?ボスからの手紙
- 研究者にとっての論文十ヶ条
- この2つを意識するだけで作文能力が劇的に上がる:cohesion(連結)とcoherence(首尾一貫)
- 科研費が不採択だったら、開示された審査結果を分析して改善点を探そう
- ただいま「所属研究機関処理中」2020年度(令和2年度)4月1日午前10時00分、科研費交付内定が通知される
- 大学における第3の職種URAとは?科研費獲得増の効果は?
- 臨床医のための 臨床研究テーマの見つけ方
- 科研費は基盤Aか、手堅くBか、審査区分は?
- 科学研究費助成事業公募要領等説明会(文部科学省・日本学術振興会主催)が開催される
- 「3た」論法とは
- まだ紙の実験ノート使って研究してるの?【電子実験ノートの浸透】
- 実験ノートの書き方
- 実験におけるポジコン、ネガコンの重要性【研究の基本的な作法】
- 平成22年度(2010年度)科学研究費補助金 新学術領域研究(研究提案型)に係る事後評価報告書(最終報告書)
- 平成23年度(2011年度)科学研究費補助金 新学術領域研究(研究提案型)に係る事後評価報告書(最終報告書)
- 平成25年度(2013年度)科学研究費補助金 新学術領域研究(研究提案型)に係る事後評価報告書(最終報告書)
- 平成24年度(2012年度)科学研究費補助金 新学術領域研究(研究提案型)に係る事後評価報告書(最終報告書)
- 【変わる科研費】新学術領域研究を見直しへ~制度の主な変更点~
- レジデントノート2月号(2019年)の特集「学会発表にトライ!」
- 効果的な科学プレゼンテーションをつくりあげる方法
- 英文校正業者の選び方と英文校正の利用の仕方
- 2019年4月1日科研費の採択が通知される
- 医学系の学術雑誌インパクトファクター 2018ランキング
- ImageJインストール方法と使用事例
- 今まで誰も教えてくれなかった「人前で話す極意」鴨頭嘉人 (かもがしら よしひと)の話し方教室
- 成功するジョブトーク(面接セミナー)のやり方
- アカデミアでの推薦状の書き方と文例(英・日)
- 生命科学研究者にお勧めの新刊・既刊
- 研究者のための科学英語プレゼントレーニング大学院講義
- 平成31年度科研費採択を目指し計画書を書く(ง •̀_•́)ง‼
- Research Statementの書き方
- 論文執筆時の注意点:曖昧さの排除
- 論文数世界ランキングで日本は6位に後退
- 大きな差を生む小さな習慣:実験ノートの効果的な書き方
- 手段はusingかby usingかbyかwithか?
- あなたが論文を書けない理由がわかる40の質問