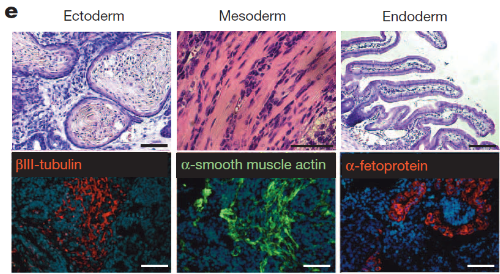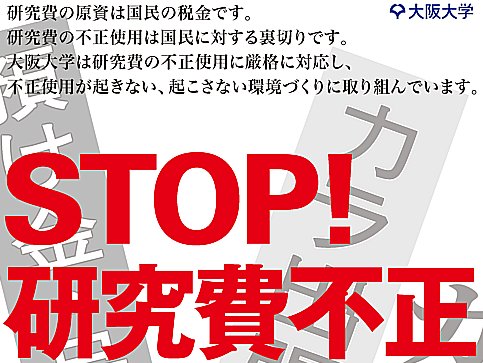理化学研究所がSTAP論文不正疑惑に関する中間報告の記者会見を2014年3月14日に行いました。各新聞社の記者や他のメディアの記者らが次々と質問をし5人がそれに答える形で会見が進み、結局4時間を越える長い会見となりました。
会見を行ったのは、
野依良治 理化学研究所理事長(ウィキペディア)
川合眞紀 理化学研究所理事(研究担当)(研究室ウェブサイト)
米倉 実 理事 理化学研究所コンプライアンス担当(ウェブサイト)
竹市雅俊 理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(理研CDB) センター長(研究室ウェブサイト)
石井俊輔 調査委員会委員長(理化学研究所上席研究員)(研究室ウェブサイト)
の5人です。
竹市理研CDBセンター長も野依理事長も今回の論文発表の不適切さに関しては、あり得ないことだと断じており、厳しい態度でこの問題に臨んでいることが伝 わって来ま した。また石井調査委員長は記者らのどんな質問にも丁寧かつ明快によどみなく答えていただけでなく、サイエンティストとし ての本音が感じられるような手厳しい見方も時折示していました。
石井俊輔調査委員会委員長が質疑応答のときに何回も繰り返していましたが、この調査委員会のミッションはSTAP細胞の真偽を科学的に立証することではなく、あくまでも今回の論文発表に関して不正行為が存在したかどうかを調査することだそうです。結局のところ、不正行為があったかどうかはまだ調査中であり結論は持ち越されました。
NATURE論文のデータは疑惑が噴出しすぎていて、どのデータはまだ正しいと考えて良いのかが混沌としていますが、今回の記者会見での野依理事の発言にもあったように、いまでもSTAP細胞の存在を信じているというのが理研の立場のようです。STAP細胞作製の再現性・追試を行っている研究者は誰なのかという質問には竹市センター長が、理研CDBの丹羽博士が行っていると答えました。
博士論文で使用した画像をNATUREの論文でも使いまわした点は意図的な捏造の有力な証拠の一つと考えられます。この中間報告で記者から「そういうことがありえるのか?」と質問されたのに対して、石井調査委員長は「かなりレア。」という表現をするに留め、調査継続中であると答えました。
川合理事は不正を立証するのは調査委員会の仕事という主旨の発言をしていましたが、むしろ、不正がなかったことを立証する責任が著者らにあるとすべきでしょう。
今回の中間報告では2つのNATURE論文で指摘されている6つの疑問点のうち2つに関しては悪意のある不正とはいえないという結論を出しており、残る4点に関しては悪意のある不正だったかどうかに関してはまだ結論が出ていない(「調査継続中」)と表現しています。
この中間報告で明らかになった一番の問題点は、調査のあり方そのものでした。例えば一つめのNATURE論文の図1で緑色に光ってきた細胞の形が不自然ということに関しては、「従って、動画からこの図を作製する過程には改ざんの範疇にある不正行為はなかったと判断される。」(PDF)と結論付けました。なるほど一意委員長の説明には説得力があります。しかし、動画からのこの図を作製する過程には不正行為はなかったとしても、みんなが一番知りたいことは、この動画を撮る以前の過程、すなわちSTAP細胞を作製する実験そのものに不正がなかったのかどうかということです。その点に関する調査報告なしに、6つの疑問点のうちの1つは解消されましたというのは詐欺的な態度です。言っていることにウソはないが、もっと大きな真実を明らかにしようとしていないからです。
NATUREの論文で他人の論文の記述を相当量コピーアンドペーストしていたというのは事実なのですから、その一点に限っても理化学研究所が定義する「盗 用」そのものであり、「研究不正」と結論できるはずです。3月14日の中間報告でなぜそのような見解が示されなかったのか、首をかしげざるをえません。6 項目のうち不正が認められなかった2項目のみを「不正が見つからなかった」と中間報告したのは恣意的な感じがします。石井調査委員長がどれほどプロフェッショナルな仕事をしても結局のところ調査報告には中立性が全く保証されていないということです。
この中間報告を受けてメディアが出した記事の中には、
「2項目は不正なし」=重要画像は「酷似」—STAP細胞で中間報告・理研 (ウォール・ストリート・ジャーナル2014年 3月 14日 15:48 JST 更新)
STAP 細胞論文「研究不正にあたらず」「継続して調査」、理研が中間報告を Web で公開(アメーバニュース 2014年03月14日 18時00分 提供:japan.internet.com)
STAP細胞問題で理研、論文画像の指摘2点について「不正に当たらない」と判断 4点は継続調査(ITmediaニュース2014年03月14日 14時21分 更新)
といった見出しをつけたところがありました。一般の読者がこれらの見出しだけ読むと「不正無し」が全体の結論だったのかと誤解しそうです。このような記事タイトルがついてしまった一番の理由は、理化学研究所が「不正があった」と受けとられそうな表現を徹底的に排除した中間報告を行ったからでしょう。新聞記者たちは何とかしてそういった言葉を引き出そうと繰り返し質問していましたが、石井調査委員長は慎重に言葉を選んでいました。
結局のところ、理研が理研の不正を調査するという構図がそもそもおかしいという至極当たり前のことが確かめられた中間報告記者会見でした。理研の影響を一切受けない外部の研究者が調査すべきです。
FNNnewsCH(フジニュースネットワーク)
(全録)「STAP細胞」論文 理研の調査委員会が中間報告(1/7)
(全録)「STAP細胞」論文 理研の調査委員会が中間報告(2/7)
(全録)「STAP細胞」論文 理研の調査委員会が中間報告(3/7)
(全録)「STAP細胞」論文 理研の調査委員会が中間報告(4/7)
(全録)「STAP細胞」論文 理研の調査委員会が中間報告(5/7)
(全録)「STAP細胞」論文 理研の調査委員会が中間報告(6/7)
(全録)「STAP細胞」論文 理研の調査委員会が中間報告(7/7)
参考
- 理研の調査委員会の中間報告の問題点 (http://stapcells.blogspot.jp/2014/03/stap.html)
- STAP細胞 研究論文の疑義に関する調査中間報告 生中継 (番組ID:lv172387382) ニコニコ生放送 2014/03/14(金) 開場:13:30 開演:14:00 この番組は2014/03/14(金) 18:08に終了いたしました。来場者数:155025人 コメント数:205642
- 研究論文(STAP細胞)の疑義に関する調査中間報告について(独立行政法人理化学研究所2014年3月14日):調査委員会調査中間報告書(全文)、調査委員会調査中間報告書(スライド資料)
- 小保方氏「いけないと思わなかった」-4時間を超えたSTAP問題の中間報告会見(マイナビニュース2014/03/15):今回の会見は、200名弱の会議室に300名を超す報道陣が詰めかけ、席が無い場合、通路に直接座るという姿も見受けられた。また、出席した理研の担当者たちは、今回の問題を重く見ていたためか、ほとんどの報道陣からの質問に真摯に答えようという姿を見せており、最終的に4時間を超す会見となった。
- STAP細胞:理化学研究所の会見一問一答(毎日新聞2014年03月14日):Q 博士論文の画像の転用について小保方さんの説明は?【石井】だいぶ昔に、骨髄由来の血液細胞を使い、このような画像を得ていた。それを間違って使ってしまったという説明だ。Q そういうことはありえるのか。【石井】客観的にみてかなりレアなケースだ。そこが調査継続中になっていることを理解してほしい。
- 【小保方氏問題 理研4時間会見詳報】(1)「未熟であったと反省の言葉を述べている」小保方氏動向に回答(産経ニュース2014.3.14 20:37)
- 【小保方氏問題 理研4時間会見詳報】(4)完 聴取時の小保方氏「心身ともに消耗した状態」(産経ニュース2014.3.15 00:02):【記者】「野依(良治)理事長、竹市さんに伺いたい。新しい論文に過去の研究結果を間違えて掲載するというのは通常の研究者として起こりうることか」 【竹市氏】「通常の研究者はこういうことは決して行いません」 【野依氏】「こういうことはあり得ない、起こりえないと思います。」
- 理研、STAP細胞・小保方氏問題について「不正かどうかは調査中だが、極めて不適切」(BLOGOS編集部2014年03月14日 18:06):