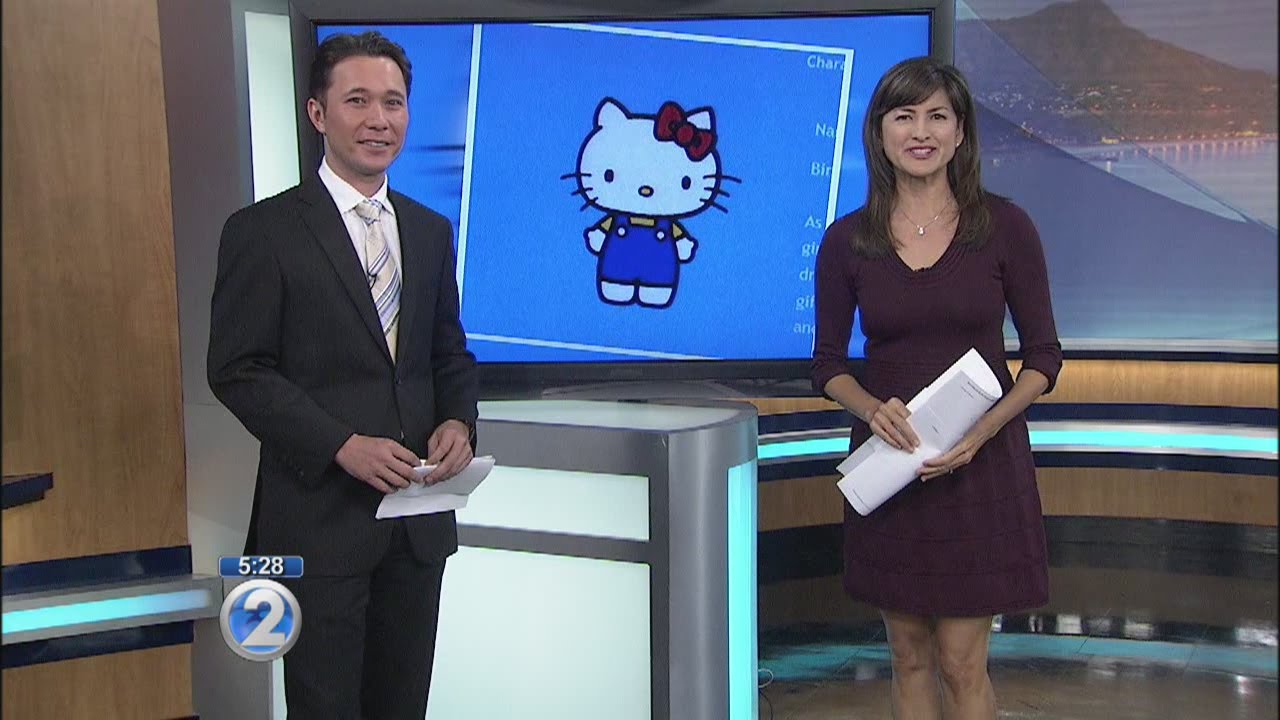小惑星探査機「はやぶさ」は2003年5月9日に打ち上げられ、2005年9月12日に小惑星イトカワに到着、イトカワを周回して観測した後、2005年11月にイトカワへ着陸してサンプルを採取、その後、燃料漏れやエンジン停止、音信不通などさまざまなトラブルを克服し、2010年6月13日に地球に帰還しました。小惑星イトカワ到着時の観測結果が2006年に、さらに、その後地球に持ち帰られたサンプルの分析の結果が2011年に、どちらもサイエンス誌上で発表されています。
サイエンス 2006年6月2日第312巻5778号 (目次)
Fujiwara et al., The Rubble-Pile Asteroid Itokawa as Observed by Hayabusa. Science 2 June 2006: 1330-1334.
Abe et al., Near-Infrared Spectral Results of Asteroid Itokawa from the Hayabusa Spacecraft. Science 2 June 2006: 1334-1338.
Okada et al., X-ray Fluorescence Spectrometry of Asteroid Itokawa by Hayabusa. Science 2 June 2006: 1338-1341.
Saito et al., Detailed Images of Asteroid 25143 Itokawa from Hayabusa. Science 2 June 2006: 1341-1344.
Abe et al., Mass and Local Topography Measurements of Itokawa by Hayabusa. Science 2 June 2006: 1344-1347.
Demura et al., Pole and Global Shape of 25143 Itokawa. Science 2 June 2006: 1347-1349.
Yano et al., Touchdown of the Hayabusa Spacecraft at the Muses Sea on Itokawa. Science 2 June 2006: 1350-1353.
ところが、はやぶさが取得した蛍光X線データに基づいて小惑星「イトカワ」の元素組成を解析した論文(Okada et al., 2006)に誤りがあったとして、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、掲載誌サイエンスに論文撤回を申し入れました。
「はやぶさ」のデータ 処理に誤り 論文撤回
“論文を執筆したJAXAの岡田達明准教授は「データの処理に問題があることに気付くべきだったが思い込みがあり、事前の予想に引きずられてしまった。共著者間の情報共有も足りなかった」と話しています。”
“論文を書いた宇宙航空研究開発機構の岡田達明准教授らが29日記者会見し、「地上の分析を参考に解析手法を構築したが、観測条件が悪くそのままでは問題があった。こうした点に注意を払わず、解析を進めたのは反省点だ」と述べた。” (時事ドットコム 2014/08/29)
データ解析にどのような不備があったのか、論文撤回に至るまでの経過等の詳細については、JAXAが公開した資料に述べられています。
「蛍光X線分光器(XRS)について」(名誉教授 加藤學)
「データ解析方法について」 (准教授 岡田達明)
「本論文の位置付け及び論文撤回に至る経緯」(研究主幹 藤本正樹)
今回の解析の問題点
(A)エネルギー較正
•蛍光X線ピークの抽出にあたり,エネルギー較正にはゲイン変動があることを仮定したが,その後の調査によりオフセットの変動で説明できることがわかった.
•Mgのピークと同定したチャンネル番号が装置由来のピークと一致しており,それと誤認した. (B)統計的有意性
•ピーク位置抽出後は,元のX線スペクトルに対して解析を行う必要があるが,誤って平滑処理後のX線スペクトルを使用していたことがわかった.
•そのため,見かけ上は統計的有意になったが,実際はランダムなノイズでも同様の結果を示す可能性が排除できない.
データ解析手順のまとめ
本論文で用いたデータ解析方法は地上の分析装置で使用されている方法を参考にした.ノイズに対する信号の相対強度(S/N)が良好なことが前提である.本論文では観測時に太陽X線が弱く,S/Nの悪い条件であったにも関わらず,そのことに十分な注意を払わずにこの解析方法で進めたことに問題があった. 結果として、「事前予想」に大きく引きずられる形で解析作業を進めることになってしまった 太陽X線強度が弱かった等の悪条件があったとしても、S/Nの悪い条件を想定してのデータ解析手法の整備を、観測をする前から進めておかなかったことが、最も反省すべきことであり今後に生かすべき教訓だと考える
(はやぶさXRSに係る論文撤回の申し入れに関する記者説明会 資料PDF1.2MB JAXA 平成26年8月29日 より)
2006年にこの著者らが蛍光X線分光データ分析により検証しようとした仮説は、後に探査機「はやぶさ」が持ち帰ったサンプルを実際に分析することにより検証され、その結果は2011年にサイエンス誌に発表された6本の論文の一つ(Nakamura et al., 2011)で報告されました。
サイエンス 2011年8月26日 第333巻6046号 (目次)(成果を解説するポッドキャスト)
Nakamura et al., Itokawa Dust Particles: A Direct Link Between S-Type Asteroids and Ordinary Chondrites. Science 26 August 2011: 1113-1116.
Yurimoto et al., Oxygen Isotopic Compositions of Asteroidal Materials Returned from Itokawa by the Hayabusa Mission. Science 26 August 2011: 1116-1119.
Ebihara et al., Neutron Activation Analysis of a Particle Returned from Asteroid Itokawa. Science 26 August 2011: 1119-1121.
Noguchi et al., Incipient Space Weathering Observed on the Surface of Itokawa Dust Particles. Science 26 August 2011: 1121-1125.
Tsuchiyama et al., Three-Dimensional Structure of Hayabusa Samples: Origin and Evolution of Itokawa Regolith. Science 26 August 2011: 1125-1128.
Nagao et al., Irradiation History of Itokawa Regolith Material Deduced from Noble Gases in the Hayabusa Samples. Science 26 August 2011: 1128-1131.
参考
- Tatsuaki Okada, Kei Shirai, Yukio Yamamoto, Takehiko Arai, Kazunori Ogawa, Kozue Hosono, Manabu Kato. X-ray Fluorescence Spectrometry of Asteroid Itokawa by Hayabusa. Science 2 June 2006:Vol. 312 no. 5778 pp. 1338-1341 DOI: 10.1126/science.1125731
- はやぶさXRSに係る論文撤回の申し入れに関する記者説明会 資料PDF1.2MB (JAXA 平成26年8月29日)
- はやぶさXRSに係る論文撤回の申し入れについて:” 当機構 宇宙科学研究所に所属する研究者が主著者となって投稿し、平成18年6月2日のサイエンス誌に掲載された論文「X-ray Fluorescence Spectrometry of Asteroid Itokawa by Hayabusa」について、本日、主著者らがサイエンス誌編集部に論文の撤回を申し入れましたのでお知らせいたします。なお、当該論文は、「はやぶさ」 に関連して発表された査読付き論文129件(うちサイエンス誌には14件掲載)の内の1件です。..” (JAXA 宇宙高校研究開発機構 平成26年8 月29日)
- JAXA、蛍光X線分光器によるイトカワの元素組成の解析に関する論文を撤回(日経テクノロジーオンライン 2014年8月30日)
- 小惑星イトカワの真の姿を明らかに~「はやぶさ」サンプルの初期分析結果~(JAXA 宇宙航空研究開発機構 2011年12月27日)
- 小惑星イトカワの素顔に迫る―「はやぶさ」科学的観測の成果― (JAXA 宇宙航空研究開発機構)
- はやぶさとは(JAXA 宇宙教育センター)
- 日本の宇宙開発の父 糸川英夫 生誕100年記念サイト (JAXA)